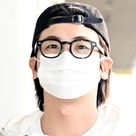イ・スンヨル「今は音楽を楽しみたい」
10asia |

イ・スンヨルとインタビューを行う約10日前、彼のニューアルバムを先に聞いて大きな衝撃を受けた。「新曲聞いてみた?」という携帯のメールに「イ・スンヨルの歴代の傑作」と躊躇なく答えるほど凄かったからだ。昨年、イ・スンヨルのライブを見ながら、次の作品に対して大きく期待した。当時、彼は過去の曲はほとんど演奏せず、深刻で実験的、さらに難解な新曲を続けて聞かせてくれた。どうしてだろう。例えば、ジャズピアニストのブラッド・メルドーの場合、ライブを通じて曲を整え、その曲がある程度、軌道に乗った時にレコーディングするスタイルだ。イ・スンヨルも同じパターンだったのだ。付け加えれば、最近のライブでイ・スンヨルは、基本的に編成されたバンドとノートパソコンを使ったサンプリング、ベトナム楽器のダン・バウを使った異色なサウンドを聞かせてくれた。そして、ニューアルバムであり、4枚目のフルアルバム「V」ではライブの面白味を覆す、驚きの結果を聞かせているのだ。これを90年代半ばに韓国大衆音楽界で鶏群の一鶴のロックサウンドを聞かせてくれたU&Me Blue(イ・スンヨル、バン・ジュンソクのバンド)の衝撃と比較するとどうなるだろうか?5月20日、10asiaの事務室でイ・スンヨルと会った。
―今年3月、アメリカのテキサス州で開かれた世界的な音楽フェスティバル「サウスバイ・サウス・ウエスト音楽祭(SXSW)」での公演を果たした。子供の頃アメリカで過ごし、現地の音楽を体得したが、今は韓国音楽業界に慣れた自分の音楽を現地の人々の前で演奏した気分はどうだったのか?イ・スンヨル:韓国に渡って長い時間が経った。僕がアメリカで暮らしていた当時、東洋人のスターはブルース・リーだけだった。これまでに東西の境界も低くなり、お互いに対する情報もたくさん増えた。彼らが認識する東洋人のイメージが無条件に良くなったとは言えないが、音楽を知らせる良い機会だったので嬉しかった。
―昨年「仁川ペンタポート・ロック・フェスティバル」では、前作「why we fail」に収録された曲は演奏せず、難解な曲だけを続けて演奏した。そのため新しいアルバムが気になった。一体どんな音楽を作るためにあのような難解な曲を演奏したのか聞かせてほしい。
イ・スンヨル:昨年の「ペンタポート」公演……そうだ。新曲中心に公演をした。昔もそうだったし、今後も変わらないと思う。ニューアルバムの公開を間近に控えた時は、公演の8割は新曲を披露する。そのようにバンドと息を合わせた後、レコーディングを始める。「V」の収録曲は昨年の4月から、外部コンサートで演奏した。
―レコーディングはいつから始まったのか?
イ・スンヨル:昨年の11月、4日間弘益大学(ホンデ)のVELOSOで6曲を先にレコーディングした。残りの4曲はその後、少しずつFLUXUSスタジオでレコーディングした。アルバムの1番目に収録された「minotaur」は、一昨年の夏から秋にかけて一番先に作曲し、「we are dying」と「who?」「犬になって」「satin camel」もほぼ同じ時期に作った。
―どのようなきっかけがありVELOSOでアルバムをレコーディングするようになったのか。
イ・スンヨル:昨年、VELOSOで4回ほどコンサートを行ったが、空間と音がとても良かった。「NAVER MUSIC ONSTAGE」を収録したことがきっかけで、コンサートをして、アルバムのレコーディングまですることになった。
―歌と楽器演奏を別々にレコーディングする一般的なスタジオ作業とは異なり、ライブ形式でレコーディングを試みた。特別な理由はあるのか?
イ・スンヨル:今までのレコーディング方式に飽きていた。一般的なスタジオ作業は歌と楽器演奏を別々にレコーディングした後、一つにまとめる。そのように実際に歌と楽器が交じり合わない、人為的に空気感(ambience)を作る作業から抜け出し、新たなチャレンジが必要だった。そのため、一つの空間で行われるバンドのアンサンブルをアルバムに盛り込むことになった。4~5回程度をレコーディングした後、ベストな演奏だけを選んだ。アルバムを聞くと分かると思うが、バンドとのアンサンブルは混沌としていた。このような楽器同士の空気感を、これまでのスタジオで作る自信がなかった。ところがコンサートの前、合奏室で練習した時はその空気感をスタジオで生かすことができた。その雰囲気を生かしたかった。
―今回のアルバムの数多くあるキーワードのひとつは、バンドのアンサンブルではないかと思う。楽器の編曲は、どれくらい演奏者たちに任せたのか?
イ・スンヨル:僕は楽器別にデモを精巧に作るタイプだ。楽器ごとに編曲が完成した後、合奏に入る演奏者の意見を受け入れる部分は、定められたリフ(繰り返されるコード)を除いて間奏の部分だけだ。ダン・バウの演奏者のプホンが作ったいくつかのメロディを除いて、基本的には自分で作ったデモとほとんど同じである。もちろんバンドのチームワークを形成することにより進化する部分もある。
―ニューアルバムでベトナムの民族楽器ダン・バウが重要な役割をしている。この楽器とはどうやって巡り会えたのか。
イ・スンヨル:偶然だった。運転中よく聞くラジオのクラシックFM(93.1)チャンネルを聞いていた時、国楽管弦楽団の演奏が流れた。現代音楽のような曲だったけど、最後に演奏された無伴奏のソロ演奏が本当に良かった。どんな楽器なのか知らなかったので調べてみたらプホンが演奏したダン・バウという楽器だった。その後、知人を通じてプホンを紹介してもらった。プホンはベトナムでダン・バウを専攻し、韓国に留学に来て国楽の打楽器の博士課程7年目である。

イ・スンヨル:最初は一緒にバンドをやってみないかと誘った。僕のアルバムとデモを聞かせたが、最初はピンと来なかったと思う。フェスティバルの単独コンサートを何度か一緒にすることで、息を合わせた。クラシック演奏者と一緒に演奏した知人の話を聞くと、コミュニケーションにおいてしばしば困難な時があると。ところがプホンは柔軟な性格だったので、僕たちと相性がぴったり合っていた。アルバム作業を始めた頃は、周りからダン・バウの役割が大きすぎるのではないかと心配する声もあった。偏ったのかと心配したところ、アルバムを聞いてみたらそれほどではなかった。
―最初アルバムを聞いた時、これまでのイ・スンヨルの音楽と違う部分は、ダン・バウの音と中東風の音階が用いられたことだと思った。どのようなきっかけでこんなに斬新な作業をするようになったのか?
イ・スンヨル:メロディは私が作ってプホンに演奏してほしいと頼んだ。今回のアルバムを構想しながら私は“おかしな音楽”に心酔していた(笑) エチオピア人ミュージシャンMulatu Astatkeのアルバムを3ヶ月くらい聞きながら、「そうだ。固定されたものだけあるわけではない」と考えを大きく変えた。個人的にアラブの音階に対する憧れもあった。お祈りをするように小声でつぶやく歌だ。これまで作ったことのないメロディを作りながら「ここまで来たら、もっと大胆になっても良いのではないかな」と考えるようになり、アラブ圏のボーカルを探した結果、たまたまプホンの伝統音楽バンドにオマールというボーカルがいて、紹介された。オマールはインディーズバンドSuriSuri MahaSuriの共同リーダーでもある。僕が意思を見せたら、憧れていた音楽の要素を少しずつ手に入れることができた。その勢いで後ろを振り向かずにアルバム作業に着手することができた。色んなことを試したことにおいて“オーバー”とは考えず、思うままに前進した。「minotaur」でナレーションをしたのはオマールのアイデアだった。小説「異邦人」から抜粋した一節を読んだものだ。
―ボーカルも変化している。イ・スンヨルの声は時々歌を歌うというより、すすり泣きのように聞こえる時がある。
イ・スンヨル:ボーカルにおいても後半作業をできる限り減らした。歌詞もメロディも自然に思うがまま歌った。スタジオではなくライブで歌う時に、音程が不安定でも僕が望む雰囲気が漂う時がある。そんな雰囲気を生かそうとした。2次的な歌詞作業を行わなかったので、そのような意図で英語の歌詞もハングルに変えなかった。
―「fear」「who?」など長い曲が特に多い。1970年代のプログレッシブ・ロック的な感じも出ているが。
イ・スンヨル:それは聞く人の好みによって違う音楽に聞こえると思う。今回のアルバムは曲のテンポが遅いため、アルバム全体の再生時間が自然に長くなっている。これまでアルバムの再生時間を考えながら曲を作ったことはない。長い曲の中で十分に余裕を持って言いたいことをすべて言うことは良いことだと思う。以前は長い曲を書く時、余計な部分まで入っているのではないかと検討したが、今はもうそのようなことはしない。今回のアルバムには、話したい物語をすべて詰め込むことができた。曲の進行上、余計な部分はまったくなかった。
―イ・スンヨルの音楽がU&me blue時代からソロに至るまで英米ロックの枠に入っていたとしたら、今回のアルバムはその枠から抜け出したと思う。
イ・スンヨル:抜け出したかった。ずいぶん前から、英米圏のロックをわざわざ探して聞いていない。運転しながら音楽を聞く時が一番多いが、ラジオは常にクラシック・国楽チャンネルになっている。おそらく、3枚目のアルバムを準備しながら、新しい音楽はほとんど聞いてなかったと思う。音楽を聞くことも楽しくなければならないが、いつからかそういう感情が消えていた。ただ、好きなミュージシャンが新しいアルバムを公開したら、気になって探して聞くくらいだった。久々にMulatu Astatkeの音楽が、酒を一杯飲む時に流す音楽だった。
―「bluey」はチャン・ピルスンがフィーチャリングした。前作でハン・デスと一緒に作業した「彼らのブルース」に続くブルース連作だと聞いたが。
イ・スンヨル:今回のアルバムの中で最初に作った曲だ。2008~2009年に書いた曲なので、アルバムの流れにおいては目立つ曲である。タイトルどおりにブルージーな曲だ。幼い頃から今までブルースというジャンル、スタイル、ソウルに対して妙な憧れを持っている。僕は歌や演奏をする時、その憧れを失わないことをもっとも大事にしている。前作はハン先生と一緒に作業をしたので、今回は女性ボーカルと一緒に作業してみたいと思い、最初に頭に浮かんだ人がチャン・ピルスン先輩だった。でも、遠くにいるし活動もあまりしていないので断られたらどうしようと心配したが、喜んで受けてくれて本当に嬉しかった。チャン・ピルスン先輩が1995~1996年頃にラジオDJをしていた時に、U&me blueが出演してアコースティックライブをしたけど、めちゃくちゃになったことがある(笑) 先輩は済州島(チェジュド)にいるので、レコーディングしたファイルをやり取りしながら作業した。作業中に電話は一度したけど、近いうちに焼酎でも一緒に飲もうと誘ってくれた。

イ・スンヨル:U&me blueの時韓国はギタリストに対する視線が限定的だと思った。ギタリストが意味することが片方に偏っていると思い、ギターを演奏することを負担に感じたこともあった。しかし、僕はギターを弾けなかったら音楽を作れなかったと思う。それはギターで曲を書いて、ステージでもギターを演奏するからだ。ギターなしで歌を歌うと集中度が変わる。そういう意味でギターは僕にとって欲望の対象であり、必需品だ。
―所属事務所であるFLUXUS MUSICのキム・ビョンチャン代表とは非常に長い付き合いだと聞いた。イ・スンヨルの第一印象について聞いたら、「すぐに商業的に成功するとは思わなかった。でも、非常に素晴らしい可能性を持った人だった」と話してくれた。
イ・スンヨル:U&me blueの1枚目のアルバムをレコーディングする時、ミュージシャンとエンジニアとして出会った。当時、キム・ビョンチャン代表はソン・ホンソプ先生が運営していたソンスタジオのエンジニアだったので、U&me blueの1枚目と2枚目のアルバムにエンジニア、演奏者、ミキサーとして参加した。以後、僕がソロでレーベルを探している時、ちょうど会社を立ち上げると聞いた。それで、“意欲過剰なデモ”を渡したが、商業的な面を見て契約したわけではないと思う(笑) たまに細かいことではなく、長い目で見て直せる部分を僕にアドバイスしてくれた。アーティストになれという要望ではなかったのでは。「兄さんは僕がスーパーミュージシャンになることを望んでいるわけではないですよね?」と聞いたこともある。どうしてそんなことを聞いたのかは覚えていないけど(笑)
―今回のアルバムに対する周りの音楽関係者たちの評価が非常に良い。「V」が本人のディスコグラフィーにおいてどの位置を占めることになるだろうか?
イ・スンヨル:さあ、よく分からない。僕は残念なことに自分の昔のアルバムをあまり聞かない。そのアルバムを作った時に肉体的精神的に苦しかった時が浮かぶようだ。むしろやりがいを感じるべきなのに、それができない。でも、3枚目の「why we fail」を作業した時は、レコーディングすることさえも楽しみたいと望んだ。そして、実際に音楽を作る苦痛が徐々に減っている。4枚目のアルバム「V」は、これからときどき聞けると思う。3枚目よりは4枚目のアルバムの方を頻繁に聞くと思う。
―1996年に出たU&me blueの2枚目のアルバム「Cry… Our Wanna Be Nation!」の中身を見ると、イ・スンヨル本人が書いた文章がある。音楽界にできるだけたくさんの選択肢が出てきてほしいと述べているが、本人はそのような作業を続けているのか?
イ・スンヨル:実は、元々アルバムのために書いたものではなく、他のところに載せるために書いた文章だった。それはバラエティ(variety)について述べた文章だ。多様性があってこそ、対案を選ぶことができるから。この頃週1回、インディーズの音楽が聞けるラジオ番組のDJを担当しているが、その中にはとても幅広い多様性がある。そして、その中にも主流と非主流がある。僕を選ぶファンたちにとって、僕が対案になれるかな?
記者 : クォン・ソクジョン、編集 : ホン・ジユ、翻訳 : チェ・ユンジョン