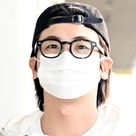チャン・フン監督「『高地戦』という徹底的に韓国らしい戦争映画を作りたかった」
10asia |
二作目の映画「義兄弟」以降、次回作が最も期待された指折りの有名監督であった。三作目の映画「高地戦」は公開前から前売り1位を記録した。デビュー作「映画は映画だ」から「高地戦」まで新しい作品を作るたびに成長する映画のように、自分の領域も広げていった彼は、この夏、超大作との戦いに“戦争映画”を持って挑んだ。これまでは莫大な予算と多くの人を動員して作られたスペクタクルな要素や、生と死を扱った新派劇の主役だった韓国戦争を、「高地戦」では戦争そのものにフォーカスを当て、観客を朝鮮戦争ではなく、休戦協定の真っ只中に呼び込んだ。協定を発効する直前の12時間もの間、韓国と北朝鮮は地図の上で1センチでも広い土地を奪うために、たくさんの命を犠牲にした。ただ生きて帰りたいと思っていた人たちはその戦場の中で生き残るために、怪物になったり、気を狂わせたりした。人間の悲劇やドラマの「背景ではなく、戦争そのものにフォーカスを当てるために」努力した時間についてチャン・フン監督に話を聞いてみた。
“実際に朝鮮戦争の時の記録写真と似ている部分が多い”

チャン・フン:戦争映画は確かに重い作品でもある。さらに韓国はまだ休戦中で解決して平和になったというわけではないので、戦争を軽いエンターテインメントとしては扱えなかった。映画の中の人物が持っている面白い姿や感情を心に訴えるように作りたかった。そうすれば、他の映画とは違う面白さを発見できるのではないだろうか。他の作品と同じ基準ではない、戦争映画としての面白さに期待してほしい。どうしても映画の予算が「義兄弟」より多いので、観客数に対する負担はある(笑)
―毎回、新しい作品を作る度に、予算が大幅に増えているが、今回、110億ウォンという製作費の運用するのはどうだったか。
チャン・フン:規模が小さい映画を作る時は時間に追われた部分があった。「映画は映画だ」を撮影する時は、日が暮れても次の日にはそのシーンが撮れないから、スタッフや俳優たちと話し合う時間さえなかった(笑)一人で決めることが多かった。そのせいで監督のすることも多かったが、今回のように予算のたくさんある映画は、話し合いもできるので、監督よりもスタッフの役割が大きいと思う。「高地戦」は監督一人で作れるものではないので、全ての部分に集中して作らなければならない。特殊効果や特殊メイク、何でも僕よりスタッフたちがやることが多かった。
―映画の製作記録を見たら、スタッフの苦労話が長々と書いてあった。苦労することが目に見えている作業だったから、事前にスタッフを説得して抱き込んでおくことがもっとも重要だったのではないか(笑)
チャン・フン:準備段階で作品についてたくさん話し合った。戦争にどんな角度から近づいていけば良いか、お互いの意見に同意して同じ考えを共有した。リュ・ソンヒアートディレクターとキム・ウヒョン撮影監督は僕よりも経験が多かったし、僕たちは同じ目標を持っていた。それを具体化させるために肉体的には大変だったが、一緒に頑張った。無理やりやらせたのではない(笑)
―「高地戦」を通して、出演した俳優たちが再評価されて、さらに期待されているが、監督として嬉しいと思う。
チャン・フン:俳優みんなそれぞれにいいシーンがある。イ・ジェフンが演じたシン・イルヨンの最後のシーンは彼にとっても僕にとっても大変な場面だった、砲弾を浴びた顔から色んな感情が溢れ出て、いい感じに撮れた。最後の戦闘シーンを間近にして、シン・イルヨンがそっと微笑むシーンがあった。どう笑うかによって雰囲気が違ってくるが、何かを知っているような微笑みに色んな感情が込められていた。イ・ジェフンの眼差しは独特な魅力があった。
―以前から戦争映画を撮りたいと言っていたが、大変なプロジェクトだから実際に決心するまで悩んだと思う。
チャン・フン:漠然としたアイデアだった。今まで映画やドラマで見慣れている素材だが、戦争という特殊な状況は人間を限界まで追い詰めていく。その人々の姿を撮ってみたかった。もちろん「義兄弟」を撮ってまたすぐに戦争映画を撮るとは思っていなかった。縁があっても、遠い未来のことになると思っていた。でもシナリオを読んだ後、こんなにすばらしいシナリオにはもう出会えないかもしれないと思い、負担にはなったが「やるしかない」と決心した(笑)シナリオを読んで一番強く記憶に残った場面は中国軍が押しかけてくるところだったが、資料調査やイメージを具体化していくと、高地や兵士たちの姿のように、今までとは違った角度から見た部分がさらに強烈に思えた。
―脚本を書いた作家のパク・サンヨン先生もキム・ウヒョン撮影監督やリュ・ソンフィアートディレクターなど、最高のスタッフたちと共に過ごした。特に撮影においては「義兄弟」のイ・モゲ監督やキム・ウヒョン監督というとても有名な撮影監督たちと一緒に仕事をしている。
チャン・フン:イ・モゲ監督も口数の多い方ではないが、キム・ウヒョン監督はもっと口数が少ない(笑)イ・モゲ監督はどんなことをしてでも方法を捜そうとするエネルギーに溢れた撮影スタイルで、様々なアイデアを出し続けている。とても動的だ。それに比べてキム・ウヒョン監督は撮影自体においては動的だが、悩むところは静的である。現場でも最後まで悩んで検討するスタイルだ。
―そんな静的な雰囲気が映画でも出ていた。戦争映画なのに、一時停止すると美しい絵のようになるシーンがたくさん見られる。
チャン・フン:映像が流れていると観客たちはドラマについて行くことしかできないが、止めてみると美しい絵がたくさんある。撮影から美術、セッティングまで、実際の朝鮮戦争の時の記録写真と似ているところが多い。
「『高地戦』では戦争そのものを先に見てほしい」

チャン・フン:その部分が重要だった。高地をもう一人の主人公だと思っていた。その山が一人の人間として、人格があるように映したかった。山が砲弾に当たってどんどん変わって行くところも、人間が怪我をして傷ついて、崩れていくように、悲しく見えたらいいなと思った。俳優をキャスティングするように高地もキャスティングしようと思った。朝鮮戦争の時の高地を撮った写真にはとても強い印象があった。戦地の荒れた光景と凄絶さよりも、悲しみを強く感じた。土地に対してこんなに悲しいと感じるのは初めてだった。だから、このような韓国らしい土地の個性を見せたかった。それが「高地戦」の向かう方向であって、「プライベート・ライアン」のような外国の戦争映画の美の本質を真似するのではなく、徹底的に韓国らしい戦争映画を作らなければならなかった。
―撮影が行われた白岩山は実際、2009年の火災で燃えている。悲劇のような事件ではあったが「高地戦」にとっては幸運だっただろう。
チャン・フン:悲劇的なことだが、その山があったから「高地戦」の撮影ができた。韓国の森はよく管理されているから木のない山はあまりない。もし誤って木を一本でも切ったら、大変な事になる。4~5ヶ月歩き回っていたが、白岩山を初めて見た時は何かを感じた。山は山でも何も感じられない山もある。何時間も走り回って、見て、「ただの山だね。次行きましょう」と言うことも多かった(笑)ところが、白岩山を見た瞬間、ここではいい映画が撮れそうな気がした。もちろん最初はスタッフと俳優たちが苦労することが分かっていたので機嫌を伺った(笑)高地もみんな人の手で作った。クレーンで大まかに整理して、残りは美術チームが頂上に上って全てセッティングした。申し訳なかったが、ありがたかった。映画を作っている時はもっと幸せで、生きていることを感じられた。全ての感覚が開かれる感じかな。それに現場ではみんなで映画のためにできることを全部やれるから。一人が夢を持っているだけでも幸せなのに、多くの人が同じ夢を持っていたら、もっと幸せだと思う。現場にいればそれが感じられる。
―朝鮮戦争は民族や理念など様々な角度で見られるが、「高地戦」では人物というフレームを通じて話を進めている。
チャン・フン:観客たちは人物を通して映画を見ているから、人を通じて表現しなければならない部分もあった。また、一人が全ての戦争を経験することはできない。誰もがその戦争の一部を経験する。同じ場所にいてもそれぞれが違う人物だから、戦争に対して違うことを感じている。それを様々な角度で見せたかった。ただ、今までの朝鮮戦争を扱った映画とは少し違ってドラマや人物たちの背景としての戦争ではなく、戦争のそのものを見せたかった。戦争がそこにいる人物たちの魅力的な橋渡しの役割になったらといいなと思った。「ブラザーフッド」の場合は兄弟の感動的な話がドラマを引っ張っていったが「高地戦」は戦争そのものをまず感じてほしかった。
―戦争そのもの?
チャン・フン:戦争そのものを題材にした映画というのも重要で、そんな試みも必要だったと思う。朝鮮戦争において他の要素ではなく、戦争そのものにフォーカスを合わせてストーリーを繰り広げることも必要だと思った。今まで朝鮮戦争の前半部分を扱う映画は多かったが、後半部分を扱った映画はなかった。それに高地戦闘は世界的にも珍しい、韓国にあった特殊な戦いだったから、それがどのように起きたのかも見せたかった。韓国らしい戦いをした「高地戦」は外国映画の戦闘場面を真似するのではなく、僕たちだけの戦争のシーンを作ることができる特別さがあった。
「頭に残る映画より、心に残る映画を作りたい」

チャン・フン:意識的にやっているわけではない。僕は“こんな映画を作りたい、こんな話に惹かれる”と考えるのではなく、ただ無意識の中で繰り広げられるストーリーの方が面白いものになると思う。今まで自分でも気づいてなかったが、そうだったようだ。女性的な話や恋愛映画も好きだけど、好きなことと作れることはまた違う。今度、女性をもう少し分かるようになったら (笑)、そして結婚したら作ってみたい。パートナーがいれば女性に対してもっと色んなことが分かるようになると思う。男のストーリーに拘っているのではなく、今は男向けの映画が楽だと思っている。
―ナム・ソンシク、キム・スヒョクといったキャラクターの名前や、高地での食べ物、品物などで韓国と北朝鮮の兵士がコミュニケーションするシーンは、作家パク・サンヨン先生の前作「共同警備区域JSA」を連想させる。
チャン・フン:似ている部分はあると思う。同じ作家の話だから十分そうなると思っていたし、作家が書いた作品を尊重したかった。それよりも「高地戦」そのものをどんな色で見せるかを悩んだ。いずれにしても前作に似ているという話は出てくると予想していた。同じ作家が書いた作品だから、その点は認めながら、積極的に僕たちだけの映画を作ることに集中した。
―その点は冷静なようだ(笑) 韓国では監督が脚本も書いて演出もしなければ、本物の作家として認めてくれない。
チャン・フン:だから初期のインタビューではそれとなく「自分が書いた作品でもないのに、それを演出しているのか」という感じで聞かれる時もあった。三作目だから僕が書いたシナリオで映画を作ってみたかったけど、“必ず僕の書いた作品でなければならない”という強迫観念はなかった。僕の書いたものが良ければそれにして、もしもっと良い作品があったら、それを選びたい。演出者とは演出をする人だから。その部分では楽に行きたい。シナリオを直接書いた先輩監督たちは本当に立派な映画を作っていて、尊敬している。しかし環境が変わりつつある今は、プロデューサーがシナリオを書いたり、作家が書くこともできる。シナリオを書いてくれる人も必要だ。そうすればいろんな作品が企画される。無理やり僕が書いたシナリオで映画を作るよりは自然に進めて行きたい。もちろん僕の持ってない才能を持った監督も多いが、僕は自分にできることをやって行きたい。無理して人の真似をすると、上手く行かない。
―今、この時点でこの映画を観客がどう受け入れるか知りたいと言っていたが、逆にどうして今「高地戦」を見せたのか。
チャン・フン:いずれにせよ否定することも、無視することもできない。今も韓国は休戦状態だから。時間が経つほど忘れがちだが、依然としてそれが韓国の現実である。最近の若い観客は朝鮮戦争がいつ終わったのか、いつ始まったのかも分からない。幼い子供たちがこの映画を見て、過去にあった悲劇を感情的に受け入れて理解してほしい。この映画は頭に残るより心に残ってほしい。
記者 : イ・ジヘ、写真 : チェ・ギウォン