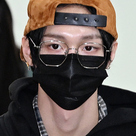「『新感染 ファイナルエクスプレス』ゾンビ物だが自信があった」NEW キム・ウテク統括代表が語る“成功の理由”
OSEN |

ゾンビが1000万人の観客を熱狂させた。信じられいない結果だった。誰一人としてゾンビ映画が1000万人の観客動員数を記録するとは思わなかったはずだ。
それもそのはず。ゾンビ映画は好き嫌いがはっきりと分かれるジャンルの1つであるためだ。大衆的ではないという意味だ。「新感染 ファイナルエクスプレス」はR指定の映画ではなかったが、ゾンビははっきり言って大衆的に親しまれる題材ではない。
それにもかかわらず、配給会社NEWはゾンビを選択し、しかも一年で最も大きな市場とされる夏の市場にゾンビ映画を出した。手綱が切れたゾンビたちは恐るべきスピードで走り回り、“1000万人突破”の栄光を掴んだ。
NEWのキム・ウテク統括代表は「自信があった。映画を観て夏の市場に出しても遜色ないはずだと判断した」と語る。キム統括代表が持つ自信は「新感染 ファイナルエクスプレス」が持つストーリーのパワーから出てきたものだった。「僕自身、ゾンビ映画は観ません」と言って大きく笑ったキム・ウテク統括代表は、ゾンビでもストーリーに力があれば可能性はあるだろうという信頼1つで、「新感染 ファイナルエクスプレス」のプロジェクトを推し進めた。そして成功を収めた。
キム・ウテク:ありがたいことだ。ジャンル的にも新しい映画だったため、果たして韓国市場でどれほどの成果を収められるか自分でも気になっていた。新しい試みをすることはトキメキと期待と不安が共存するじゃないか。そういう意味で考えると有意義な作品だったし、我々に新しい方向を示してくれる作品だったと思う。観客の方々に喜んでもらえて、それを見てこれからどのように進めば良いかを考えさせられた作品だった。様々な面で意味があった。

キム・ウテク:基本的にこの映画が持つ長所や短所は明確だと考えている。ゾンビというジャンルに対する不安の声が多かったが、監督や制作陣たちはその部分を一番大衆的なものに変えるために努力した。醜いゾンビシーンは減らして、ゾンビ物を通じたドラマにフォーカスを当てなければならないと思った。このようなジャンルの映画がドラマのほうにアピールできれば、ジャンル的な限界を克服できると考えたのだ。今回「新感染 ファイナルエクスプレス」の1000万人突破を見て、ジャンル映画にも1000万人という基準点を超えることのできる市場が形成されているということが、映画産業全般からみて嬉しかった。「このジャンルはせいぜい数万人だ」とか言うじゃないか。今回感じたのは、韓国の観客の市場拡大の展開が速いということだった。非常にポジティブだ。実は、最初は不安の声が多かった。僕自身、ゾンビ映画をあまり観ない(笑) しかし、シナリオの段階から全社員が熱狂的に好んでいた。そして編集の過程で基本的に確信があった。ヨン・サンホ監督の1番の強みはストーリーにある。ストーリー展開力が優れている。しかし、アニメ監督に初の実写映画を、しかも100億ウォン(約9億千万円)の映画を任せる冒険は、簡単ではない決定だったが、ストーリーの力を信じたし、十分可能性があると思った。
―「新感染 ファイナルエクスプレス」の成功から学んだことはあるか?
キム・ウテク:ある瞬間から会社の成長が伸び悩んだが、これは自然なことだと思った。それを通じて得るものが多いから意味があると思った。そのような意味で大変だったというよりは、その期間で良い経験をしたと思う。しかし、残念だったのは、我々も認識しないうちに我々が典型的な映画を作ろうという姿勢に変わってきたということだった。そんな姿が結果的に我が社のアイデンティティを揺さぶっていた。そのような面で「新感染 ファイナルエクスプレス」はリスクはあったが、挑戦的な作品だった。新しくならなければならないという我々のアイデンティティにおいて、もう一度基本的に我々が持つ原動力に共感できた作品だった。「新感染 ファイナルエクスプレス」という作品でその共感を形成した点は意味があると思う。
―ヨン・サンホ監督特有の社会批判的な視線が「新感染 ファイナルエクスプレス」では薄れているという評価もある。資本に屈したのかという声もあるが。
キム・ウテク:監督との葛藤は全く無かった。メッセージは変わっていないと思う。彼のカラーは変わらなかったと思う。弱くなることはあっても、基本的に伝えられるメッセージは同じだと思う。アニメは少ない予算で自由に表現できるジャンルであり、100億ウォンの映画は大衆的にアピールする作品だが、同じメッセージを届けたと思う。その部分に対して、会社の中で意見の相違があったわけではない。一度もそんなことはなかった。
記者 : キム・ギョンジュ